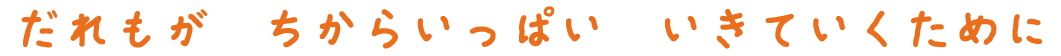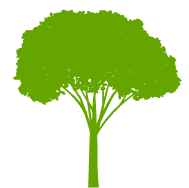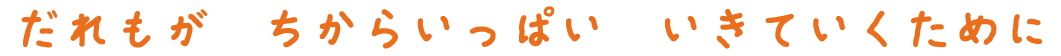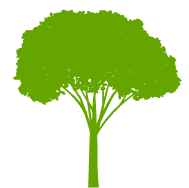|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建築2022年4月完成
|
|
|

|
|
|
|
|
|
| |
|
★
情報公開(処遇改善加算への取り組み変更)生活サポートネットワーク・ほっとラインでは、介護保険サービス、障害福祉サ...
★
7月1日-新着:☆彡月の会報Vol 39(7月)☆彡
社会福祉法人青丘社 ほっとライン 2025年7月 「月の会報Vol 39...
★
6月17日 93歳スーパー利用者さん
ほっとラインデイサービスには、仕事を頼めば、誰よりも丁寧、スタッフのよう...
★
6月4日
社会福祉法人青丘社 ほっとライン 2025年6月 「月の会報Vol 38...
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
|
差別をなくし、共に生きる市民運動、地域活動の延長線上に、1988年ふれあい館が設置されました。「自分の人生をあきらめない」という市民のねがいと共感の広がりの中で、困難を抱える人たち、生きづらさを抱える人たちが、あきらめることなく、「今日よりいい明日」を目指して、「この指とまれ」方式で仲間とつながり、市民事業を立ち上げてきました。 私たちは、わがままなほど小さな地域を大切にしながらも、高齢者、障がい者が地域社会の亀裂と分断をつなぐまちづくりの主体として活躍できる共生のまち「さくらもと」のまちづくりに寄与します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|